土地活用コラム
迷惑行為をする賃借人に対して、賃貸借契約を解除できるか
「賃借人が近隣に大音量で音楽をかけるなどの迷惑行為を続けている場合、
賃借人は契約解除をして賃借人を退去させることができるか。」

1.一般原則
①賃借人は、賃料を支払う義務を負うとともに、契約又はその目的物の性質によって定まる用法に従い、賃借物を使用収益する義務を負っています。(民法第594条、同法第616条)そして、建物賃貸借契約における賃借物であるアパートの部屋は、他の賃借人も含めて入居者が日常生活を営む場であり、賃借人は他の入居者や近隣の住民に迷惑をかけないで部屋を使用することが義務づけられており、これを「用法遵守義務」といいます。
②そうしますと、賃借人が「夜中」に騒音を発生させたり、「大声」で騒いだりすることは、他の入居者へ迷惑を及ばす行為であり、用法遵守義務違反に該当することになります。
③したがって、賃借人や管理会社から再三にわたる注意や警告をしたにもかかわらず、賃借人が近隣への迷惑行為を繰り返す場合には、賃借人は賃借人の「用法遵守義務違反」を理由として契約を解除し、部屋の明け渡しを請求することができます。
④他人に迷惑をかけないということはいわば常識であり、「当たり前のことではないか」と思われたと思います。しかし、実際に裁判してでも退去させるとなると、迷惑の「内容」と「程度」が問題となり、なおかつ「証明」というハードルがあるのです。
2.「迷惑行為」とは?
①まず、契約解除が認められる迷惑行為となるかどうかは、日常生活する上で「社会通念からして受忍限度を超えるか否か」により判断されることになります。例えば、音については、音の発生する「時間帯」や人の声や機械の動作音やひっかき音などの「種類」、そして音量の大きさや頻度の「程度」等によります。いわゆる生活音や瞬間的なものは対象になりません。
②マンションのような共同住宅の賃貸借契約では、賃借人の近隣の迷惑となる行為すなわち義務違反の提訴が著しく、賃借人と賃借人間の信頼関係が破壊されるに至っているときは、賃借人は催告することなく賃貸借契約を解除することができるという裁判例があります。また、賃借人が隣室の音は生活音程度であったが、故意に隣室の壁を叩いたり、大声で怒鳴ったりするなどの嫌がらせ行為を続け、隣室の入居者を退去させた事案で、同様に、信頼関係の破壊を容認し、賃借人は催告することなく賃貸借契約を解除できるとした裁判例もあります。
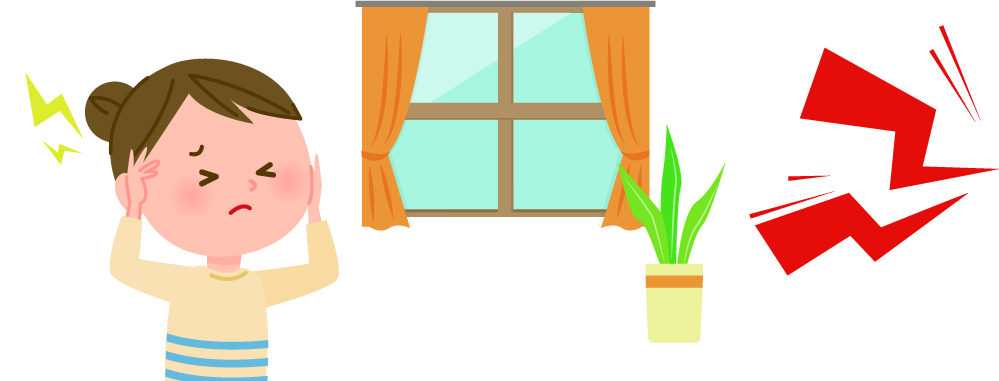
③とはいうものの、生活上の騒音は、電車や飛行機の騒音のように「デシベル」で数値化できるものではないので、実際のところ「騒音」についての照明は難しく、むしろ「複数人」から「複数回」にわたって「同じような苦情」が出ているという「事実の積み重ね」で証明するしかないのが現実です。
3.オーナーがとれる対策としては
苦情の申出をオーナーが放置することは、賃料の対価として、「平穏な生活住居を提供」するという賃借人の義務に違反することになるので、何らかの対応をとる必要があります。
①まず、苦情を申し出た賃借人から事情を聴きます。その際、「いつ」、「どんな種類の音が」、「どの程度続いていたか」を確認します。中には、病的に神経質であったり、クレーマー気質な人もいて、「その程度は我慢しなさいよ!」という申出もあると思いますが、まずは相手の話を聴くことが大事です。
②その上で、騒音元がハッキリしているときは、「近隣から申出があったこと」を伝えます。この段階では「クロ」と決めつけず、あくまで「申出があった事実」と「心当たりがあれば配慮してください」と伝えます。
③騒音元が特定できないときや、騒音元が特定できても悪質性が小さいときは、苦情の申出内容を、共用部に掲載するか、お知らせ文書を各戸にポストインするとよいです。
④そして、悪質で看過できないような場合、申出人には、「今後同じようなことがあったときは、記録して証拠化してください」とアドバイスしてください。
⑤両隣とか複数戸から同じような苦情があったときには、「クロ」の可能性が高くなります。その場合には、貸主としては厳しい対応をとる必要があり、「今後同様の申出があったときは契約を解除します」と騒音元に警告書を送付するなどします。
⑥それでも改善が見られないときは、建物明渡しの裁判を起こすことも検討することになります。
4.「音」と「騒音」をめぐるトラブルは多い!
①「音」や「騒音」以外の迷惑行為として、「共用部に大量の私物を置く」という苦情もあります。ただ、「音」と違って、残置者の特定は容易であることが多く、残置状況も写真に撮れば簡単に証拠化できるので、貸主から写真を突きつけて注意すれば、撤去されて解決する場合が大半という感じです。
②「音」と「騒音」について、日常生活に伴うトラブルとしては、例として以下のようなものがあげられます。

これらは入居者の常識とマナーによるところが大きいのですが、例えば「楽器の演奏は禁止」という特約をつけることで、ある程度の効果はあります。ただし、特約であれこれ禁止してしまうと、そもそも入居辞退をためらって避けられかねません。特に「音」の関係は子どもが関わっていることが多く、長野市では近隣住民による騒音苦情がきっかけで、公園が閉鎖されたことは記憶に新しいところです。
③かつて「『賃借人は入居者同士のトラブルについては一切責任を負いません』という特約は有効ですか?」と尋ねられたことがあります。しかし、賃借人の根本的な義務である「平穏な生活住居を提供」を否定するものなので、裁判では「無効」となると思われますし、そもそも当事者同士での解決に任せると、かえってトラブルが大きくなり、他の入居者にも悪影響を与えると思われます。
土地活用についてのご相談はこちらから



